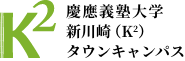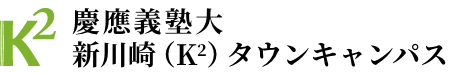「少子高齢化社会で持続的な運用ができる自動運転」とは
大前 学 (環境情報学部 教授)

自動車の自動運転は、深刻な働き手不足に悩む少子高齢化社会において、人やモノの移動の切り札となる技術です。大前学教授の研究室では、2022年5月から始まった湘南藤沢キャンパス(SFC)での自動運転シャトルバス運行によって知見を積み重ねている他、無人運転に対応した実験車両の構築も進めています。自動運転の現在地と今後の展望について、大前先生にお話を伺いました。
自動運転シャトルバスが公道を含むコースを、毎日運行
Q 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で走行している、自動運転シャトルバスについて教えてください。
大前:SFCの総合政策学部・環境情報学部エリアと看護医療学部エリアを結ぶ循環バスを2022年5月から毎日運行しています。大学構内である私道部分が1.3km、両キャンパス間の公道部分が0.9km、合計2.2kmのコースで、学生や教職員の日常的な移動手段となっています。
車体に取り付けたLiDARと呼ばれる距離センサーやRTK-GNSSと呼ばれる高精度な測位装置などの情報をもとに、ハンドル・アクセル・ブレーキをアクチュエータによって自動で操作しています。運転士が同乗し、必要に応じて手動運転による安全維持を行う自動運転であり、いわゆる「レベル2」(部分運転自動化)の段階です。運行状況のモニタリングや、ソフトウェアの更新は新川崎(K2)タウンキャンパスから行うことができます。

大前:私たちの研究室では、2000年から自動運転の研究をスタートし、システムやアルゴリズムを開発してきました。従来は、開発した技術を短い時間の実験走行により評価、確認して終わり...という流れでした。この自動運転シャトルバスについては、SFCのバス運行を担う神奈川中央交通(株)の意欲的な協力もあって、定常運行が実現しました。また、このプロジェクトは、座組のないオープンな取り組みですので、興味を持ってくださった企業が技術やリソースを提供してくださっています。例えば、私道部に塗装してあるターゲットラインペイント(日本ペイントホールディングス(株)様)、デジタルツイン情報(構内の人や車の位置)(ソフトバンク(株)様)、信号情報((株)京三製作所様)などです。これまで大きな事故やトラブルはなく、得られた知見をもとに改善をしながら運行を続けています。
Q 定期運行実施から2年が経過し、どういった知見が得られましたか。
大前:従来の研究でやっていたような短い時間の走行実験では、見いだせなかったような課題や事象にたくさん出合いました。毎日運行するので小さなトラブルや機器類の消耗・故障は当然出てきます。天候や交通状況なども様々で、運行当初に予想できなかった事象への対応が必要です。監視やシステム修正を研究者が遠隔操作できる体制にしていますが、日々のトラブルにまず対応するのは運転士さんである、という前提にも配慮が必要です。
研究では発想の独自性やアルゴリズムの先進性を競うのが常ですが、このプロジェクトでは、そんなものよりも(笑)、大事なのは安全性・信頼性です。運転士さんが判断しやすいよう操作画面を改良したり、円滑な走行のために歩行者に走行状態をアナウンスする電光掲示システムを追加したり、地道な改良をひとつずつ重ねています。


Q 「デジタルツイン・キャンパスラボ」プロジェクトとの関係を教えてください。
大前:慶應義塾大学SFCキャンパスでは、構内の人の動きなどを検知し、デジタル化された仮想的なキャンパス情報を配信、そして活用する「デジタルツイン・キャンパスラボ」プロジェクトが行われています。この一環として、自動運転シャトルバスも、構内の自動車や歩行者の位置や動きや、固定カメラで撮影した信号情報などが提供されるので、右折時の判断(遠方から高速で接近する車両の有無が分かる)、信号通過の判断に役立っています。
「二重系の自動運転機構を持つ大型バン」が
日本のラストワンマイルを救う
Q 現在開発中の自動運転実験車について教えてください。
大前:いわゆるレベル4とされる完全無人の自動運転では、車体や運行システムが故障したときに、どのように安全を確保するかということが大きな課題です。ここで言う故障とは、センサーのみならず、電源、アクチュエータ、コンピュータなど全て関係します。
今回構築している実験車は、レベル4の自動運転に対応した研究を可能とする実験車で、ひとつの車体に二系統の運転システムを搭載するべく、作業を進めています。通常時に使用している機器に不具合が発生したとき、電源も動作システムも完全に独立したもうひとつの機器(バックアップ系)が作動して、安全に停止するまで操作を行うことを想定しています。バックアップ系の役割は「安全を確保しつつ運行を停止する」ことなので、フルスペックである必要はありません。バックアップ系のセンサーや制御にはどのような性能が必要かなどの課題を検証して、研究を進めていく予定です。

Q 研究のベース車両について教えてください。

大前:2年以上にわたる自動運転バスの運行を行って、「車体の信頼性」の重要さを認識した我々が選んだのは、トヨタ自動車の「ハイエース」。今の日本で自動運転に期待されているのは、いわゆるラストワンマイルの問題解決です。地方に行くと、ハイエースなどのバンがこのラストワンマイルの移動に大活躍しています。毎日運行するということを考えると、堅牢で部品の入手や修理が容易なロングセラーカーをベースとするのが良いと考えました。
ベース車体に、二重系の機構を持つアクチュエータや電源装置を組み込み、運転席と助手席以外の8シートを脱着可能なシートに換装しました。脱着可能なシートにより、車室内を自由にレイアウトできますので、人の移動だけでなく、荷物の配送車、ドローンや小型移動ロボットの基地としての利用を研究できると思っています。車両の改造は福祉車両をカスタマイズできる専門業者に依頼し、法令に準拠した仕様になっているので、一般公道を走行できるナンバーも取得しています。
自動運転シャトルバス同様、座組のないオープンな取り組みですので、業種を問わず企業の皆さんのご参加を歓迎いたします。
日本が目指すべきは
「90歳、100歳になっても運転できる社会」
Q 自動運転の未来について、先生の見解を教えてください。
大前:自動運転の研究開発は、大きく2つの方向に分かれています。ひとつはオーナーカー(自家用車)の分野において、自動運転の技術により、安全性の向上や運転負担の軽減を実現する方向です。
もうひとつは、バスやタクシー、トラックなど公共交通の分野において、自動運転の技術により、ドライバー不足や少子高齢化に対応する無人運転を実現する方向です。
後者の方向における自動運転の研究開発は無人運転を可能とするレベル4を目的とする風潮があります。しかし現実的な社会実装となると、私は「完全無人化は不可能ではないが、コストが膨大に跳ね上がる」と考えています。運転士が乗っていれば、車体の不具合などの突発的なトラブルに対応できますが、完全無人化を目指すとなると二重、三重のセキュリティシステムが必要になります。車体だけではなく、信号や道路などインフラ側にも自動運転の安全確保のための整備をして、しかも1カ所でも故障があると事故や運行停止につながりかねない、となると維持コストも膨大なものになるでしょう。
Q 日本企業による自動運転の技術開発は、どの着地点を目指すべきだとお考えですか。
大前:資金力が鍵を握る完全無人運転の実用化は、豊富な開発費と豊富な運行実績から得られた知見を持つアメリカや中国の企業に優位性があるように思います。一方で日本企業は、自家用車の自動運転に関する良い技術をたくさん持っています。公共交通よりも自家用車の方が台数が圧倒的に多く、市場規模も大きいので、自家用車の自動運転の研究開発に商機を求めれば良いと思います。
自家用車は、言うまでもなく人が乗るものなので、完全無人にする必要はありません。バスやタクシーについても、運転士さんの仕事が運転以外にも乗客の対応や料金の収受など多岐にわたる中、運転席から人を排除することが本当に正解でしょうか。
人と自動運転技術の調和を目指すことが、日本社会にとっての最適解だと思います。完全無人を目指すのではなく、自動運転技術により、ドライバーが90歳、100歳になっても活躍できるようなシステムを実現することで、みんながハッピーになると考えています。

研究以外のエピソード
タイ留学をきっかけに始めたゴルフ
2019 年度に1年間タイのタマサート大学に留学しました。タイの駐在さんの心得みたいな情報に「タイではゴルフができないと生きていけません」とあったので、留学直前にゴルフを習いに行きました。留学後は、月1回~2回の頻度で教職員や旧友とプレーを楽しんでいます。練習をしないので全く上達しませんが、親交を深める場としてとても楽しく「もっと早く始めていれば良かった」と思っています。
プロフィール
1995 年東京大学工学部産業機械工学科卒業。97 年同大学大学院工学系研究科修士課程修了、2000 年同大学院博士課程修了。博士(工学)。慶應義塾大学環境情報学部助手、専任講師、助教授を経て、2013 年より現職。専門分野は機械工学(機械力学・制御、自動車工学)。自動車の自動運転、自動隊列走行、遠隔監視・操作における車両制御技術の研究を行っている。